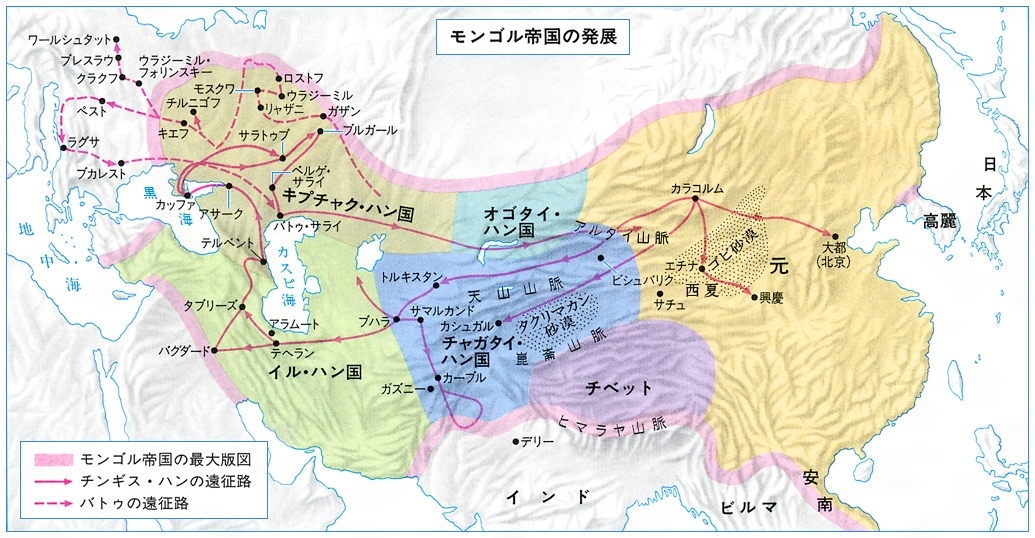2023年の新しい大河ドラマ『どうする家康』がはじまりましたね。
2022年の『鎌倉殿の13人』が、大河らしからぬ大胆な題材だったり演出だったりで話題になったところだけど、『どうする家康』はどんな感じになるだろうか。
実は近年の「攻めた」大河と言われた2019年の『いだてん』や2016年の『真田丸』や2012年の『平清盛』の翌年には、それぞれ『麒麟がくる』『おんな城主 直虎』『八重の桜』という、割と保守的なタイトルが放送されている。
この振り子の法則が今回も当てはまるようであれば、『鎌倉殿』の翌年である今年は、保守なターンなのかもしれない。
この大河は誰狙い?
NHKという放送局がおもしろいのは、日本全国津々浦々どこでも視聴できる公共放送で、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで幅広くターゲットにしつつ、同時に地上波の中では最先端カルチャーやアートに対するアンテナがどこよりも高いっていう、相反する面があるところ。
そんなNHKらしさはもちろん大河ドラマや朝ドラでもたびたび発揮されてきたんだけど、ただ、たまにそのバランスが崩れて、メインの客層である高齢者がついてこれないところまでいってしまうことが時々発生する。
最近だとドラマ内で時系列が激しく交錯する『いだてん』は視聴者を選ぶようなところがあって、後期高齢者のうちの両親は早々と脱落していた。
とがったクドカン演出よりも、無難すぎるほど無難な大河のほうが、彼らは安心して見られるとのことだった。
SNSの盛り上がりを見ていると忘れがちなんだけど、大河ドラマってメインの客層はやっぱりそっちなんだよな。
それでいうと、『どうする家康』はターゲットにしている層がすごく明確。
まずは大河ドラマのメイン層である高齢者をしっかりと掴みつつ、これまで大河ドラマを見たことがない若い女性を松潤効果で狙いにいってるといった感じでしょう。
何よりもまず、主人公が徳川家康っていう、日本で義務教育を受けていたら100%知ってる大物っていう時点でめっちゃ守りの姿勢だし、しかも演じるのが松潤っていうことで視聴率の獲りにいき方も安全牌そのものだし。
その上、織田信長の岡田准一、豊臣秀吉のムロツヨシ、武田信玄の阿部寛と、有名なライバル大名たちに濃い人たちをあてて、これでもかというほどわかりやすいキャラ設定になっており、「まんが日本の歴史」っぽさがある。
さらに、大河ドラマ恒例の、本編が終わったあとに流れる歴史の舞台を紹介する2分ぐらいのコーナーがあるんだけど、ここって歴代ずっとNHKアナウンサーのナレーションと無人の映像のみだったところが、今年は松重豊のナレーションと松潤が登場するようになっていて、そんなところにもNHKの意気込みを感じるんだよな。
大河ドラマの味わい方
そんなわけで、去年か今年から大河ドラマを見るようになった方々は非常に多いと思われるんだが、なんといっても一年間、約50話の長丁場になるわけで。
せっかく見始めた大河から途中で脱落してしまわないように、大河ドラマを見続けてきたわたくしから、独特の味わい方をいくつかお伝えしようかなと思っております。
で、最初に結論から言いますと、平成以降の大河ドラマで重要な軸になっているのは、ズバリ親子と夫婦。
いろんな時代をテーマにしたドラマが作られてきたんだけど、この2つはだいたい共通していたはず。
歴史上の人物の一生をドラマ化するにあたっては、戦とか政治とかの公的な活躍だけを描いてもドラマとしては成立すると思うんだけど、大河ドラマは主人公の家庭のシーンをかなりしっかりやる。
歴史好きおじさんだけが喜ぶだけの武張ったものにしてしまうのではなく、ホームドラマ好きの男女にも楽しんでもらえるつくりになっているんだよね。
そこで大事なのが親子と夫婦って要素。
親子の軸
大河ドラマってだいたい一人の主人公の波乱万丈の一生を描くものなんだけど、波乱万丈になるからには、生きているうちに日本社会が大きく変化して、主人公はだいたいそこに巻き込まれて揉まれて成長していくようにできている。
日本の歴史でわかりやすく社会が変化するといえば、幕末か戦国時代。
この2つの時代はとにかく大河ドラマの舞台になりやすい。
で、ドラマの中で主人公が新しい世の中を作ろうとしたり、否応なく巻き込まれていったりするにあたり、旧世代の価値観を代表する存在として出てくるのが、主人公の親。
大河ドラマを習慣的に見ている高齢者が自分を投影するために、愛情深く主人公を見守りつつも新しい価値観には戸惑うばかり、みたいな親キャラは必要なんだよね。
『青天を衝け』の「とっさま」役の小林薫とかね。
夫婦の軸
日本に今のような一夫一婦制が定着したのは明治時代になってから。
大河ドラマの舞台になるような時代には、イエ同士の関係性を安定させたり跡継ぎを産んでイエを存続させることが結婚の最大の目的だったので、恋愛結婚なんてものはまず存在しなかったし、当主は側室をもつのも当たり前のことだった。
しかし、大河ドラマの視聴者は当たり前だけどみんな一夫一婦制で恋愛結婚してきた現代人なので、結婚に関する価値観が登場人物とは大きく違う。
その差を埋めて、安心して見ていられるようにするため、史実ではどう見てもバリバリの政略結婚だったとしても、ドラマの中ではお互い好き同士として描かれるのが一般的だったりする。
側室をもつことについても、主人公はあまりその気がないが家臣たちが強く勧めるので仕方なくそうする、といったような描き方になっていることが多い。
現代人の価値観で見てもドン引きさせないような描き方でありつつ、史実には沿わせるという、かなり難易度の高いストーリーさばきが求められるところなので、ぜひ大河ドラマをみるときには結婚の描き方にこそ注目してほしい。
そういったチャレンジがうまくハマると、えもいわれぬ味わいになることがある。
たとえば全体としてあまり評判がよかったとはいえない『江〜姫たちの戦国〜』において、宮沢りえ演じる淀が、秀吉に心を許す流れは印象深かった。
人命の軽さと身分の感覚
現代人の価値観とのギャップでいうと、恋愛観と同じかそれ以上に落差があるのが、人命の軽さや身分の感覚。
戦国時代や幕末の日本人って、みんなびっくりするほど簡単に死ぬし、殺す。
また、当時の感覚では身分の差があることが当然であり、高い身分の者の命のほうが重いとされてきた。
ただここもあまりリアルに描きすぎると、見ている現代人は完全に置いていかれることになるだろう。
「信長様のやり方はおかしい」みたいなセリフを主人公や周辺の誰かに吐かせることで、見ている側が共感できる余地を用意していたりするし、主人公は身分による差別を受けることはあっても差別する側にはまわらないようにもできている。
主人公はあくまで、人の命の重さや身分の差を現代人と同じように考えているようなキャラ設定にされることが一般的であり、間違っても「何百人死のうがかまわん!」とか「身分をわきまえよ下賤が!」とか言わない。
大河ドラマを見続けていると、見事にここのラインは守られているなといつも感心する。
規定演技のこなし方
大河ドラマは基本的に、国民的な知名度がある時代や人物を扱う。
かつては『山河燃ゆ』や『琉球の風』といったマニアックなテーマで制作された大河ドラマもあったけど、近年は、新島八重や井伊直虎といったあまり知られていない人物を主人公にすることはあっても、舞台が幕末や戦国時代なので結局織田信長や勝海舟みたいな有名人は登場するからわかりやすいよねっていうパターンが多い。
そうなってくると、歴代の大河ドラマの中で、歴史上の有名なエピソードが何度も描かれることになるし、有名な人物をいろんな人が演じることになる。
そういった有名なエピソードをどのように扱うかは、大河ドラマの大きな味わいどころのひとつ。
たとえば『真田丸』での関ヶ原の戦いや本能寺の変の扱いが話題になったのも記憶に新しいところでしょう。
大河ドラマには時代考証というスタッフが存在しており、歴史上の出来事を嘘なく描けているかチェックするようになっている。
たとえば、本能寺の変のとき秀吉は備中高松城を攻めていて徳川家康は堺にいたってことは歴史上の事実として明らかなので、それと矛盾する脚本は書けないということ。
ただ逆にいえば、史実にあること以外は自由に解釈できるということでもあるので、明智光秀が本能寺の変を起こした動機だったりとか、その日のテンションみたいな部分に関しては脚本家の腕によって幅をもたせられる。
歴代の明智光秀で個人的に印象に残っているのが、『利家とまつ』でショーケンが演じたやつ。
『鎌倉殿の13人』では、源平合戦の規定演技を、三谷幸喜がどのように処理するのかが見ものだった。
源平ものといえば歌舞伎や講談などで千年以上も語られまくってきた有名エピソードの宝庫なんだけど、その中でストーリーの本筋に関係ない「扇の的」とか、嘘っぽい「安宅の関の勧進帳」とかはばっさり省略されていましたね。
『どうする家康』の規定演技
さて、徳川家康という人も、江戸時代を通じて神格化されており、あることないこと含めいろんな有名エピソードをもっているわけで、『どうする家康』ではそのあたりをどう描くのか注目したい。
特に、最初にしてもしかしたら最大の悲劇になりそうなのが、瀬名(有村架純)の最期。
信長の娘が告げ口したとおりの悪人として描くのか、それとも完全な言いがかりであんなことになってしまったとするのか。
あとは石川数正(松重豊)のまさかのあの展開についても、これまでいろんな説が言われてきた事件なので、今回はどういう解釈になるのか、とか。
もちろん武田信玄との対決だとか、本能寺の変の前後の立ち回りとかも見ものだし、これを書いてる第3話の時点では出てきていない本多正信や石田三成といった重要人物がどういうキャラになるかって観点もあるし、まあいろいろ期待ですね。
松潤はタヌキになるのか
大河ドラマって、主人公の一生を描くにあたり、青年期から晩年までを同じ俳優が演じるのがセオリーになっている。
志半ばで死んでしまう坂本龍馬や織田信長あたりは別として、だいたいみんな最終回にかけて年老いて死んでいくわけで、そういうところもきっちり演じるものなんですね。
つまり、あの松潤がですよ、秀吉亡き後のドロドロとした権力争いを演じるっていうことです。
『平清盛』の松山ケンイチとか『鎌倉殿』の小栗旬は、権力を手にした後におかしくなっていく「老害」的な感じを見事にやってたんだけど、徳川家康の一般的なイメージとしてよく言われる「タヌキ親父」な面を、松潤はどれぐらいやるのかっていうね。
今のところ三河の弱小大名としての家康は、いろんな災難に巻き込まれたりして「どうする?」と問われる側なんだけど、これが豊臣秀吉の晩年、内大臣になったあたりからの家康の立ち回りといえば、むしろ自分が争いの中心になって周囲に「どうする?」と圧をかける側にまわるじゃないですか。
豊臣につくのか徳川につくのか、どうする?って。
そのとき松潤はどんな感じになるのか、ちょっと想像もつかないんだけど。
やっぱりタヌキをやるんだろうか。
それとも、一般的には周囲を巻き込む側だったとされているタヌキ期についても、実は内心ヒヤヒヤし続けていて、「どうする?」って問われていたっていう新解釈を見せてくれるんだろうか。
「豊臣恩顧の大名たちを引き連れて上杉征伐の名目で江戸まで出てきたのはいいけど、ちょっとみんなに怪しまれてきてる…どうする?」とか、「もしも豊臣秀頼が関ケ原まで出陣してきたら、今はこっちに味方してる福島や黒田もみんな寝返りかねない…絶体絶命…どうする?」とか、「このまま大坂城を攻めたら孫の千姫の命が危ない…かといってこんな大軍勢をいつまでも大坂に集めていたら外様大名が不穏な動きをするかもしれない…どうする?」とか。
余裕しゃくしゃくだったように思われる晩年のエピソードも、こうやってドラマチックに「どうする?」な感じに描いてくれたらフレッシュでおもしろいかもしれない!
とまあ、妄想はこれぐらいにして、今日の話をまとめると、『どうする家康』に限らず大河ドラマに共通する味わい方としては、①恋愛観や身分の感覚など現代人と落差がある部分をどう感情移入できるように描くか、②歴史上の有名エピソードや有名な人物をどんな解釈で描くか、という、集約するとこの2点ってことです。
この2点を頭の片隅において時々思い出しながら大河ドラマを味わえば、きっと年末まで楽しく完走できるはず!