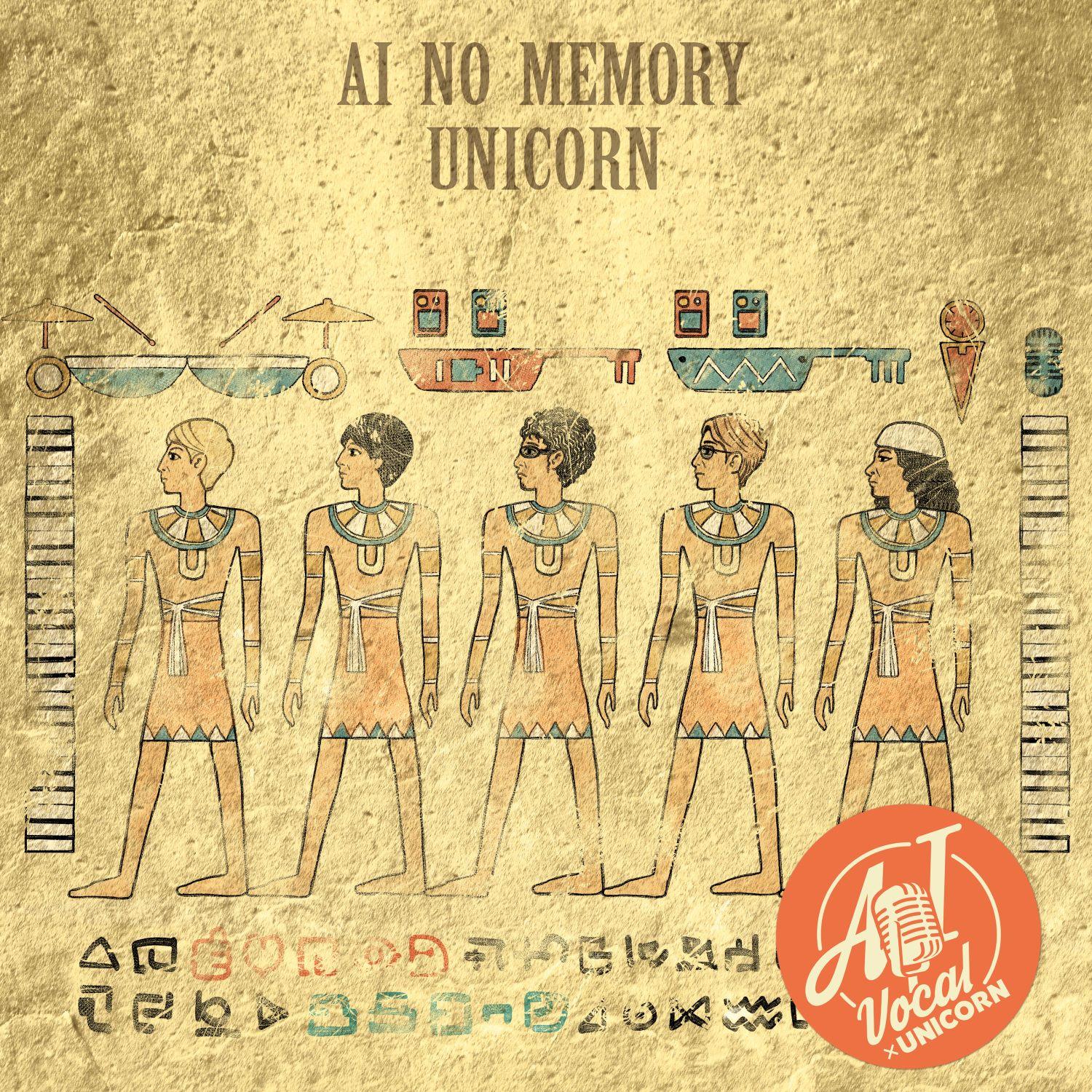ディズニープラスオリジナルの配信ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』。
これを書いている時点では全8話のうち第5話まで公開されており、全世界で大ヒット中らしい。
1980年に三船敏郎主演でドラマ化された作品のリメイクとして、ハリウッドの大資本でリッチに制作され、しかも主演の真田広之がプロデューサーとしても細かく監修していることで、日本人から見ても違和感のない描写になっていると話題の大作。
【真田広之はいつ寝ていた?】「SHOGUN 将軍」現場で、主演&プロデューサーとして八面六臂の活躍 メイキング映像披露 : 映画ニュース - 映画.com
ちなみにこれが1980年版。
舞台は戦国時代末期の日本。
日本を支配していた太閤の死後、大老たちが繰り広げる権力争いに、ポルトガル人とイギリス人の宗教対立が絡むというストーリー。
この大枠については史実の通りなんだけど、登場人物は実在の人物をモデルにした架空の存在。
たしかに、そうしたほうが史実通りよりも絶対わかりやすい。
史実との違い
主人公の吉井虎永のモデルは、徳川家康。
太閤秀吉から江戸を中心とする関東地方を任されていた大老、という設定も史実通り。
太閤の死後の取り決めを有名無実化するような振る舞いを繰り返していたというところも、幼い頃に人質に出されていたというところも、史実通り。
漂着したオランダ船の乗組員を保護して家来にしたというのも。
細かい話をすると、吉井家は高貴な血筋であるといった台詞が出てくるが、実際の徳川家も源氏の血筋であるとされていた(自称)。
この虎永と、細川ガラシャをモデルにした鞠子の設定については、だいたい史実に沿っているといって差し支えない。
(最後どうなるかはまだなんとも言えないけど)
ただ、虎永と対立する石堂和成については史実と大きく異なる点があって。
石堂のモデルは関ヶ原で家康と戦った石田三成なんだけど、史実との大きな違いとして、石田三成は大老ではなかった。
司馬遼太郎が書いていた例え話でいうと、太閤秀吉という創業社長が死んだ後に跡目争いをする有力支店長や子会社の社長たちが大老だとしたら、石田三成は社長秘書室長みたいな存在。
つまり、子分がたくさんいるわけでも、自らの腕力でぶんどった領地があるわけでもなく、後ろ盾である太閤がいなくなってしまうと、まことに心細い状態ってこと。
そんな石田三成が、一筋縄ではいかない大老たちに声をかけて味方につけ、なんとか家康と対立できるところまでこぎつけたのが史実の関ヶ原の戦いなのです。
だからこそ石田三成側から見た関ヶ原はおもしろいし哀しいし最高なんだけど、『SHOGUN 将軍』を見る世界中の視聴者にはわかりにくくなってしまうので、石堂を実力ある大老という設定にした狙いはよくわかる。
あと、樫木藪重には、特定のモデルは存在しない。
第5話の時点では、虎永の配下でありながら石堂に内通するよう誘われ、どちらに対してもいい顔してる状態。
『SHOGUN』と同じく、史実でも太閤秀吉亡き後、日本中の大名たちが徳川家康と豊臣側の間で揺れ動いていた。
樫木藪重は、そんな揺れ動いていた大名のひとりであり、特定のモデルは存在しないけど、個人的には黒田官兵衛っぽさを感じる。
豊臣秀吉の天下統一を軍師として支えた功労者でありながら、能力が高く野心家すぎて信用されなかったとも言われており、また秀吉の死後はいち早く家康に忠誠を誓う世渡り上手なところもあった。
あと、史実で三浦按針が漂着した豊後黒島は、当時の黒田官兵衛の領地のすぐ近くだったりもする。
奇しくも、藪重役の浅野忠信が北野武監督の『首』で演じていたのが黒田官兵衛なんだよね。
これ、もう藪重が黒田官兵衛にしか見えなくなるでしょ。
他にも大谷吉継がモデルであると思しき大老のこととかいろいろあるけど、また別の機会に。
あなたも「日本」に迷い込む
プロデューサー真田広之の貢献もあって、細かいところまで出来がよすぎて忘れがちなんだけど、『SHOGUN 将軍』は、イギリス人の目から見た異文化としての日本を描いた作品。
なので、名誉のために命を簡単に捨てるとか、身分の違いにうるさいとか、なんていうか東洋的な無常観みたいな、そういう西洋との価値観のギャップをことさら強調してくるところが正直ちょっと鼻につきはする。
まあ、グローバルなターゲットに向けてつくられてる作品だから、日本文化に対してリスペクトしつつ珍しがって触ってくること自体は、もう仕方ないと思う。
視聴者が感情移入するのは、異世界に迷い込んだイギリス人である按針なので、『アバター』や『ラスト・サムライ』のようないわゆる「白人酋長モノ」の構造にならざるを得ない。
未開で野蛮だと見下していた異文化に暮らしているうちに、いつしか原住民たちと心を通わせ…っていう。
そう考えると、最初の方に貼った1980年版の紹介動画にあった、「あなたも「日本」に迷い込む」というコピーは本当によくできているなと。
日本人が『SHOGUN 将軍』を見るにあたっては、異世界としてのカギ括弧付きの「日本」に迷い込むことになるわけで。
『SHOGUN 将軍』と『どうする家康』、そして『首』
去年の大河ドラマ『どうする家康』は、最後の10話ぐらいが『SHOGUN 将軍』と同じ時代っていうことになるけど、あの感じが、自国の歴史をドラマ化するにあたっての王道なんでしょう。
家族を愛し、仲間を大事にし、ライバルにも敬意を払い、勝利のために努力するっていうような、現代を生きる視聴者と地続きの感情移入できる存在として戦国時代の武士たちを描くやり方。
つまり、同じ時代を取り上げながら、あくまで外側からの目線である『SHOGUN 将軍』とは真逆の方向からのアプローチになっている。
ただ、同じ時代を内側から取り扱うにしても、かつての日本ではもうちょっと違うアプローチだったと思うんですよね。
たとえば歌舞伎なんかでは、主君を守るために我が子の命を差し出したり、親の仇を討つために子供が人生を賭けたりするし、それがストレートに美談として受け取られてきた。
主君や親や家が自分の命よりも大事っていう価値観に基づくストーリーって、昭和の途中ぐらいまではわりとストレートに感情移入できていたんじゃなかろうか。
戦後もしばらくはラジオの有力コンテンツだった浪曲も、忠臣蔵とか侠客ものが人気ネタだったというし。
それと比べると、『どうする家康』的な人権感覚に馴染んでいるわれわれは、『SHOGUN 将軍』を見ているときも、もはやイギリス人の按針の目線になっている部分はあるだろう。
本当の意味で、戦国時代を内側から感情移入することができなくなっているわけで。
あ、念のためだけどそれが悪いことだとは全然思わないですよ。
だって家とか主君とかより自分の命のほうが絶対大事だし。
ちなみに、内側/外側の話だと北野武監督の『首』は、ちょっと特殊なアプローチだったので最後にその話も。
ちょっと前に当ブログで『首』についてこんなふうに書いた。
『首』のおもしろさとしては、そんなヤクザな武士たちを、敵の首を切るという行為や首そのものに対して異様なまでに執着する存在として描いているところ。
まるで、いけにえだとか干し首だとか纏足だとか贈与みたいな、現代日本人には理解しがたい風習をもつ異民族の一種みたいな感じ。ほとんど文化人類学の領域。
日本の内側からでありながらも、武士という存在をヤバい他者としてあえて突き放して描いた北野武のアプローチはあらためてすごいと思いました。










![第74回NHK紅白歌合戦」キービジュアル - ヒゲダン「紅白歌合戦」で全国の中学生とコラボ、「Chessboard」歌唱動画を募集 [画像ギャラリー 2/4] - 音楽ナタリー](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2023/1113/kouhaku_74th_KV01.jpg?imwidth=750&imdensity=1)