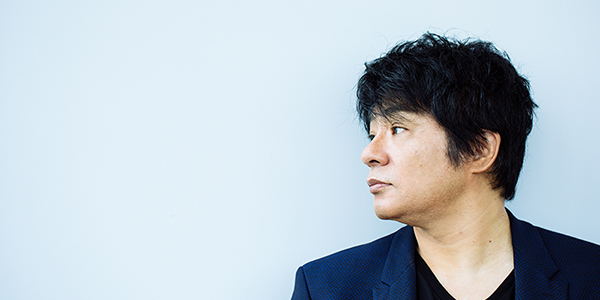科学ネタとして消費されるヘヴィメタル
Twitterとかでよく流れてくる、好きな音楽ジャンルによって性格がわかるとか、音楽を聴かせるとワインがおいしくなったとか、そういうアカデミックな装いをした記事あるでしょ。
だいたいそういう記事においては、メタルとクラシックとヒップホップとEDMなんかを比較した感じになっていて、「メタルのような音楽を好むタイプはこんな傾向が…」または「パブリックイメージとは違って案外メタル好きは‥」みたいな語り口になってるじゃないですか。
そういう記事を掲載するウェブメディアにとって、粗野で過激で頭悪そうなヘヴィメタルのパブリックイメージと、それを裏付ける or 覆すような意外な研究報告って、まあPV稼ぐのにもってこいのネタなんでしょうね。
ヘヴィ・メタル、自動車の運転に悪影響を及ぼすという新たな研究結果が明らかに | NME Japan
「ヘヴィメタルは死と向き合う助けになる」という研究結果 | ギズモード・ジャパン
【研究報告】男性ホルモンの多い男はソフトロックやヘビーメタルがお好き | BUZZAP!(バザップ!)
ヘビメタファンの性格を英大学が調査「彼らは権威を嫌い、自尊心が低い」 - ライブドアニュース
タイトルに興味をひかれて思わずタップして読みにいった経験は誰でもあるはず。
それがもし「R&Bのファンは…」っていう記事だったら果たしてどれほどの人が読もうとするかと考えると、まあキャッチーでおいしい路線を見つけたなって思うよ。
ただそこに愛を感じることはほぼなく、まあお手軽に消費されてるなって感じしかないけど。
「メタル脳 天才は残酷な音楽を好む」
そんな風潮にあやかったのかどうか、こんな本が出版された。

- 作者: 中野信子
- 出版社/メーカー: KADOKAWA
- 発売日: 2019/01/30
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
近年いろんなメディアでひっぱりだこの脳科学者、中野信子さんの著書ですね。
さっき挙げたような一連の記事で、科学ネタとしてのメタルのキャッチーさは認識されているし、そこそこ売れる確信があって世に出されたんだろうなという気はする。
個人的にはどうしても嫌な予感があったけどね。
どうせまたあの雑な感じで消費するんでしょって。
せいぜい揚げ足とってやろうかというぐらいの気持ちで手に取ったのだった。
そしたらですね、パラパラとめくったら章の終わりごとに著者が好きなメタルバンドを写真つきで紹介するページがあって、しかもカーカスみたいなエクストリームな音のバンドまで登場してるじゃないか。
さらにプロローグを読んでみたら、中野さんかなりのメタル好きとのこと。思春期の不安定で鬱々としたメンタルをメタルによってだいぶ救われたみたいなことを仰ってる。
これは失礼しましたって話で、さっきの先入観を捨ててかからないとダメだなと思った。
本当にメタルが好きな人が書いてるのであり、そして脳科学者の看板を掲げて堂々と書いてると。
そこらの出どころの怪しい3流ウェブメディアの飛ばし記事とは違って、適当なことはしていないであろうと。
これはってことで、さっそく腰を据えて本編を読み始めたのだった。
威勢のいい看板と慎重な書きぶりのギャップ
「メタル脳」は、帯に「モーツァルトよりメタリカを聴け」と書かれているとおり、メタルを聴くことが他のジャンルと比べてどれだけ脳に良いかを専門家として語っている本。
見出しのタイトルを読むだけで、「メタルを聴くと頭が良くなる」「メタルは反社会的ではなく非社会的」「内向性が高い人はメタル好き」などとあって興味深い。
「メタルは世界の欺瞞を見抜く」とまで言われたらそりゃ気になりますわな。
メタルに支えられて10代を過ごした人なんだし、よもや雑に扱ったり貶めたりしていないだろうという信頼感もあるしね。
ところが、いざ読んでみると「可能性があると言えます」とか「メタルである必要性は〜必ずしもありませんが」みたいな慎重な書きぶりがやけに目立つ。
「メタルを聴くと頭が良くなる」っていう大上段にかまえた章でも、結局「これはあくまでわたしの推論ですが」かよっていう。
なんていうか、慎重っていうかむしろ腰が引けてるような。
メタルを安易に科学ネタとして消費してるウェブ記事を読んだときに誰もが感じる「それってメタルじゃなくても大音量の音楽だったらなんでもよくね?」とか「この話のキモってメタルだからってことじゃなくて好きな音楽を聴いたらどうなるかってことでは?」みたいなツッコミどころが、残念ながらこの本にも散見されるわけですよ。
そこで妄想
全編にわたってそんな感じで、威勢のいい看板と慎重な書きぶりのギャップが目立つわけ。
これ、もしかしてだけどこんなやり取りで書かれた本なのではないかって妄想したくもなるよね。
編集者「中野先生!なんかないすか、ヘビメタ聴いたら賢くなるみたいなやつ、ないすか」
中野さん「なにをもって『賢い』とするかもいろいろありますよね、うーん…」
編集者「あのほら、ヘビメタのライブに来る人ってすごく暴れたりして怖い感じしますけど、ああいうのが実は…みたいなのあります?カラオケでストレス発散のすごいバージョンみたいなやつとか?
中野さん「(いや、カラオケと比較…さすがにそのまんますぎて書けないな、わたしは暴れるタイプでもないし…どうしよ)」
編集者「うーん、ほら、なんか実は脳の特定の部位がこうビビッときてるんだとかそういう」
中野さん「ああ、たとえばライブではCDでは出ていない可聴域の音が出ていて、それを耳だけじゃなく皮膚でも感じることで、オキシトシンが分泌されるというのはあるかもしれないですね」
編集者「おお!そういうのですそういうの!」
中野さん「ただ可聴域の話だと別にヘヴィメタルに限らずライブ全般に当てはまっちゃいますけどね」
編集者「いやいやいや!いいじゃないですか!そういうのもっとください!」
中野さん「(これも書きぶりでバランスとらないとな…)」
編集者「あのほら、ライブですっごい頭を振るやつなんでしたっけ?あれは脳にいいんですか?」
中野さん「ヘッドバンギングですね。いや、特にそういう話は聞いたことないですね」
編集者「なんかそういうことにできないですかね?血行が良くなってとかでも」
中野さん「むしろちょっと脳損傷のリスクがあるので推奨できないです、すみません」
編集者「(チッ)」
みたいな感じで作られていったのではないかと邪推してしまう。
タイトルで強めの断言をした後に本文でフォローするパターンが何箇所か見られるのは、その押し引きの痕跡かなと。
強い気持ち強い愛
ただこれ、文化人気取りの学者が数時間ぐらい語りおろしたものを編集者が文字起こしして適当にまとめたような安易な本っていうわけでもなさそう。
中野さんにとってメタルが切実なテーマであることはビシバシ伝わってくるし、むしろ脳科学の知見に基づいて語っている部分よりも、実体験から組み立てられた論のほうが説得力が桁違い。
たとえば、メタルファンはニセモノを憎む気持ちが強いとか、世間のみんなが付和雷同で飛びついているものにノレないとか、そういう傾向を深堀りして説いていく第4章などは、面目躍如といったおもむき。
(世界的にポピュリズムの流れが強まっているこの時代、安易に尻馬に乗らず欺瞞を見抜くメタルファンの特性が重要になってくるとのことです!)
それは、鬱々としていた10代のあの頃、メタルを聴くことで「別に孤立していても構わないのだ」という安心感を得られたと語る第1章と呼応しているかのようで、エビデンスに基づいた説得力というよりも、実体験に基づく思いの強さがとにかく伝わってくる。
強い気持ち、強い愛。今のこの気持ち、ほんとだよね。
ハロウィンは犬臭い
本書でも言及されてるけど、どんな音楽を好むかでその人がわかるっていう。
それでいうと、会ったことないけど中野さんのことをすごく好ましく感じた。
カーカスのような複雑な構造のバンドが好きだけど、ハロウィンはなんだか「犬臭い」感じがして好きになれなかったとか、ロブ・ハルフォードのメタリックで「なめらか」な質感の声は好きだけど、サミー・ヘイガーやデヴィッド・カヴァーデイルの声が苦手だとか、自分語りがさらに脱線したところに垣間見えるかわいげ。
そしてグイグイくる編集者(妄想です)に対して、社会人としての大人の対応と学者としての誠実さの板挟み(妄想です)でバランスをとってがんばる姿(妄想です)も素敵。
そして何より、世間が顔をしかめるような音楽に傾倒することで自分をどうにか保とうとしていたという件への共感がすごい。
高3の秋にマイケル・モンローのデモリッション23の来日公演を一緒に見た京都の高偏差値女子校のあの子、今頃どうしてるかなとか思い出したりもした。
この曲の歌詞を覚えて来日公演のとき歌ってたあの子。
「ロシアンルーレット・セックス!」って大声で合唱した姿が今でも忘れられない。
「科学的に証明されています」
サラリーなマンとしての仕事柄、いろんなデータを分析して何らかの結論を出すっていうことを日常的にやってる。
もともとそういう定量的な分析からこぼれ落ちるものに興味があった人間だってこともあり、グラフだの関数だのはすごい苦手だったけど、いまじゃBigQueryも使えるようになった。
その経験から言えるんだけど、「科学的に証明されています」とか「データによると」ほど胡散臭いものはない。
けっこうなんとでもなるんだなって。
いい加減な分析をもっていっても突っ込まれるかどうかなんて、結果を見る側(上司とか教授とか読者とか)の能力にめっちゃ依存する。
だいたいみんな忙しいし、ザルだよね。
「メタルが好きな人は◯◯だ」も、「メタルを聴くと◯◯になる」も、まずは疑ってかかったほうがいいと思う。
最低限、それってメタルじゃなくても成り立つのでは?と考えてみるといいと思います。
さらにいうと、その「メタル」は具体的に何なのか?
デフ・レパードとブルータル・トゥルースでは全然話が変わってくるぞと。
「カレーの王子様」と「LEE 40倍」をどちらもカレーでしょって言って何かを語ろうとするやつが信用できないのと同じだぞと。
そこまで指摘できるといいと思います。
メタルを聴くとそういったリテラシーを養えます。脳科学的に証明されています。